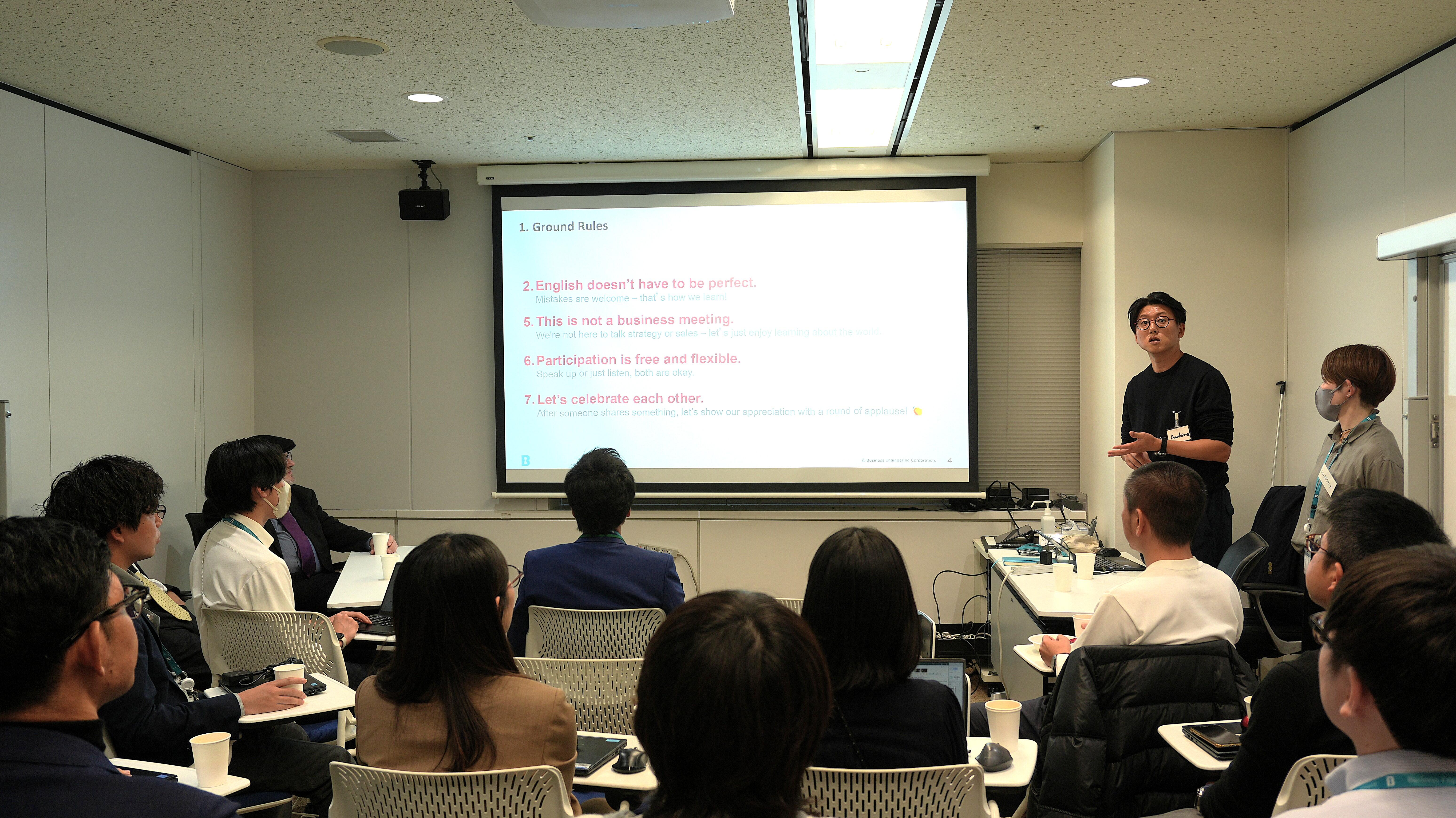話者:ビジネスエンジニアリング株式会社
ソリューション事業本部
デジタルビジネス本部 AI&Dataバリューデザイン部
副部長
守屋 伶香(もりや さとか)
現代のビジネス環境においてデータは企業戦略の中心的な要素であり、それをいかに活用できるかが成否を分ける。企業のデータ活用を支援するビジネスエンジニアリング(以下、B-EN-G)でその任を担うのが、入社11年目の守屋伶香だ。大学院時代に身につけた統計学のスキルと入社以降のプロジェクトで培った製造業の知見を武器に、データ利活用コンサルタントとして活躍。IT活用と業務改善コンサルティングを組み合わせつつ、綿密な計画立案とプロジェクト管理によって、複数のデータ利活用プロジェクトを成功に導き、担当する顧客から高い評価を得ている。

活躍の場を得られる会社で着実にステップアップ
守屋の強みは、ゴールを決めたらそこにたどり着くための方法論を探り当てて、ゴールに至るまでのルートを設定し着実に成し遂げていく部分にある。大学院でデータ解析を経験し、原因の発見だけでなくプロセスを掘り下げて理解することに面白さを感じた。そしてITとデータ分析を駆使するコンサルタントになることを決意。複数の会社からオファーを得たが、その中で守屋が自己実現のために選択したのはB-EN-Gだった。
「B-EN-Gは、少数精鋭で若手のうちから自らの裁量でプロジェクトに携わり活躍できる会社という印象でした。優秀な先輩方もいて、自分を試せるだろうと。私が持つ統計解析のスキルをしっかりと認めてもらえたことも大きかったです」(守屋)
B-EN-Gでのキャリアは、SAP BPM導入プロジェクトでの開発担当から始まった。その後、大手設備製造業向けSAP ERP導入プロジェクトに原価管理コンサルタントとして配属され、約2年間で要件定義から設計・開発・テストを経てリリースまでを経験。システム導入の全行程を一通り担うことで、業務プロセスの理解を着実に深めた。
次の大手食品会社向けSAP ERP導入プロジェクトではチームリーダーに抜擢され、同じく2年にわたる大規模プロジェクトでリリースまで完遂。続く大手化粧品会社向けプロジェクトでは、さらなる活躍の場を広げ、プロジェクト中盤からプロジェクトリーダー(PL)に抜擢され、プロジェクトの終わりまで完走した。こうした経験を通じて、業務を深く理解する経験に加え、チームを導くリーダーシップも磨かれていった。
この時点では、会社はそのまま守屋をSAPのプロジェクトマネージャー(PM)として育成していく計画であった。しかし、プロジェクトの経験を積むなかで本人がより強く抱くようになったのは、業務データを経営や現場のためにより一層有効に活用したいという思いであった。ちょうどその頃、社内にデータ活用のコンサルティングを行うための組織を立ち上げるという話が浮上する。
「プロジェクトを経験するなかで、企業に蓄積されたデータが十分に活用されていないことに疑問を抱いてきました。DXは進んでいるものの、多くは部門内にとどまり、全社的なデータ活用の事例はまだ少ないのが実状です。大手製造業であれば高度なデータ活用が可能であると確信し、その実現を支援したいという思いから、自ら志願してデータ活用の部署への参加を希望しました」(守屋)

自身初のデータ利活用プロジェクト 顧客から高い評価を得て、企業内で拡がる
本人の真摯な思いは会社に届いた。そのまま立ち上げの中心メンバーとなり、そこから守屋はデータ利活用コンサルタントとして活躍を重ねていく。
データ利活用コンサルタントとして初の現場は、大手医薬製造業において製造プロセスで異常を検知するためのデータ分析環境を整備するプロジェクトだった。モデルを使った多変量解析でより高度化した異常検知を実現したいという理由から、B-EN-Gに声が掛かり、守屋がPMとして参画した。
医薬業界の知見はなかったため、守屋はまず業界の理解から入り、議論に臨むために有識者から見解を聞き、参考論文を精読し、学会も聴講しながら知識を得ていった。そこから分析ツールと手法の見直しを開始し、製造工程プロセスの分析と改善策の検討を繰り返した。
異常検知をする際、従来は約1,200種類の業務プロセス関連データのうち、30項目未満の重要項目での単変量解析に限られていた。守屋は、複数変数間の「相関崩れ」を捉える異常検知を目指し、次元圧縮※によりデータを簡素化した上で、全データを対象とした分析を提案した。
「検証を進めた結果、原因分析につながる示唆が得られました。異常がほとんど起こらない医薬品製造プロセスにおいて、教師なし学習の主成分分析(PCA)は有効だという判断になり、いくつかの取り組みを通して業務データに適した分析手法を確立することができました。」(守屋)
この取り組みは、1工場の特定ラインの1製品を対象にスモールスタートで開始したが、活動の成果に手応えを感じた顧客側の責任者により、その後複数のライン、工場へと広がり、同時に業界向け情報誌で発表されるに至っている。
(注釈)
※ 次元圧縮とは、データが持つ意味や構造を可能な限り損なわせずに、データ内の変数の数(次元数)を減らす技術のこと。
さまざまなパターンのデータ利活用プロジェクトを成功に導く
最初の成功が次なる案件を呼び込み、続いて守屋は大手消費財会社のプロジェクトに分析リーダーとしてアサインされる。同社では、需給チームがSAPの計画系ソリューションであるSAP IBPに搭載された需要予測機能を活用して販売予測を立てていたが、期待通りの成果が出ないという課題を抱えていた。原因としては、ツールに実装されたモデルをそのまま使用し、自社に適したデータ活用ができていないことが想定された。守屋はこの課題に対し、重回帰分析の手法を提案。クラウド上に分析基盤を構築し、納品実績のほかに同種商品データ、テレビ広告量や競合他社価格、当時まん延していたCOVID-19の罹患者数などの政府統計データを変数要素として数式に入れて数十万のモデルを作り、機械学習によってその中から最適なモデルを選択することで、予測精度を大幅に向上させた。
このケースでは手法選びもさることながら、守屋のチームマネジメント力とプロジェクト推進力が顧客から高く評価された。
「当初はお客様も半信半疑でしたが、月2回程度のコミュニケーションを重ね、予測精度の向上と業務運用に耐えうるモデル管理手法の整備を同時に進めました。担当事業製品の8割における予測精度向上という厳しい目標に対しては、段階的なマイルストーンを設定し、チーム編成やメンバーの能力発揮を工夫することで、お約束通り1年で目標を達成しました」(守屋)
その後も守屋は、新たなパターンの分析案件へ取り組んでいく。次に参加したのが大手物流企業の倉庫業務の安全管理を目的としたプロジェクトで、B-EN-Gのペーパーレスソリューションであるmcframe RAKU-PADで収集したデータを、安全対策に活かしたいというものであった。
このケースでは、まずデータを見て業務を理解し、それに適したデータ分析の解決策を定義するところから着手した。解決策として、報告者が思い思いに入力した情報に自然言語解析を使用し、事故が発生しやすい状況を分析。事故につながったケースとつながらなかったケースを比較し、後者で実施されていた教育内容から事故防止に有効な取り組みを特定。効果の高い施策が一目でわかるダッシュボードを構築した。

業務を理解することから始め顧客には小さな成功体験を積み重ねてもらいながらゴールに進む
先に紹介したプロジェクト2件が分析の高度化を目的としたものだったのに対し、後者はゼロからの取り組みだ。その後も守屋は条件が異なる数件のプロジェクトへ柔軟に対応してきたが、「やっていることの本質は変わらない」と話す。
「データ解析やIT技術のスキルはもちろん重要ですが、特に大切にしているプロセスはお客様の業務理解です。課題に向き合うには、背景にあるビジネス思考や業務構造にも着目します。お客様と分析目的やKPIを特定することで、『どの手法を選択するか』や『機能をどう実現するか』といった真に価値あるデータ分析を見極めることができます」(守屋)
もうひとつ、冒頭で述べた通り守屋の特長はゴールに至るまでのルートを設定し、それを実現するための方法を考え、確実に突き進んでいくところにある。そのためにデータ分析だけでなく、業務プロセスの改善提案や社内のボトルネックを解消させるための調整・手法の提案まで行う。そしてプロジェクトを進める際には、逆算して3カ月程度ごとの目標を顧客に設定してもらう。次にB-EN-Gからその目標を実現するための具体的な手法を複数提示し、最適なものを選んでもらう。このサイクルを繰り返すことによって顧客は小さい成功体験を積み重ねながら着実にゴールへと向かうことができる。
「このプロセスを通して、より精度の高い分析が可能となり、お客様は当初の期待を上回る成果を得られるようです。最初に受け取った課題とは異なる解決策をソリューションとして提供することも少なくありません」(守屋)
守屋が目指すのは、データ分析を通じて顧客の業務・意識に変革をもたらすこと、つまり表面的な改善にとどまらず行動や考え方そのものに変化を促すことだ。とある顧客からは「データ分析の結果はもちろんだが、それ以上に新しい気付きを貰えた。プレゼントをありがとう」という言葉をもらったという。
このようにして守屋は、データ利活用プロジェクトを通じて顧客から高い評価を得ており、名指しでお呼びがかかることも増えている。そして今ではシステムに依存しない業務データ解析を広く扱う部としての活動が社内で認知され、機械学習やAIなど各種データ解析を専門とするメンバーが次々と集まり、少数精鋭部隊として機能するに至っている。
「データ利活用を始めるにあたって、大掛かりな準備は必要ありません。まずはチャレンジして取り組むことが大切で、今ある手元のデータからでも大きな価値につながる成果が生まれるものです。私たちは製造業の皆様に対して、組織的な機運の醸成も一緒に考えながら最適なデータ利活用の環境を用意していくことができます」と守屋は語る。
これまでにデータ利活用の方法論も蓄積してきた守屋には、新たに副部長という肩書が加わった。今後も仲間とともに活躍の幅をさらに広げ、B-EN-Gによる製造業への貢献の新たな可能性に果敢に挑戦していく。