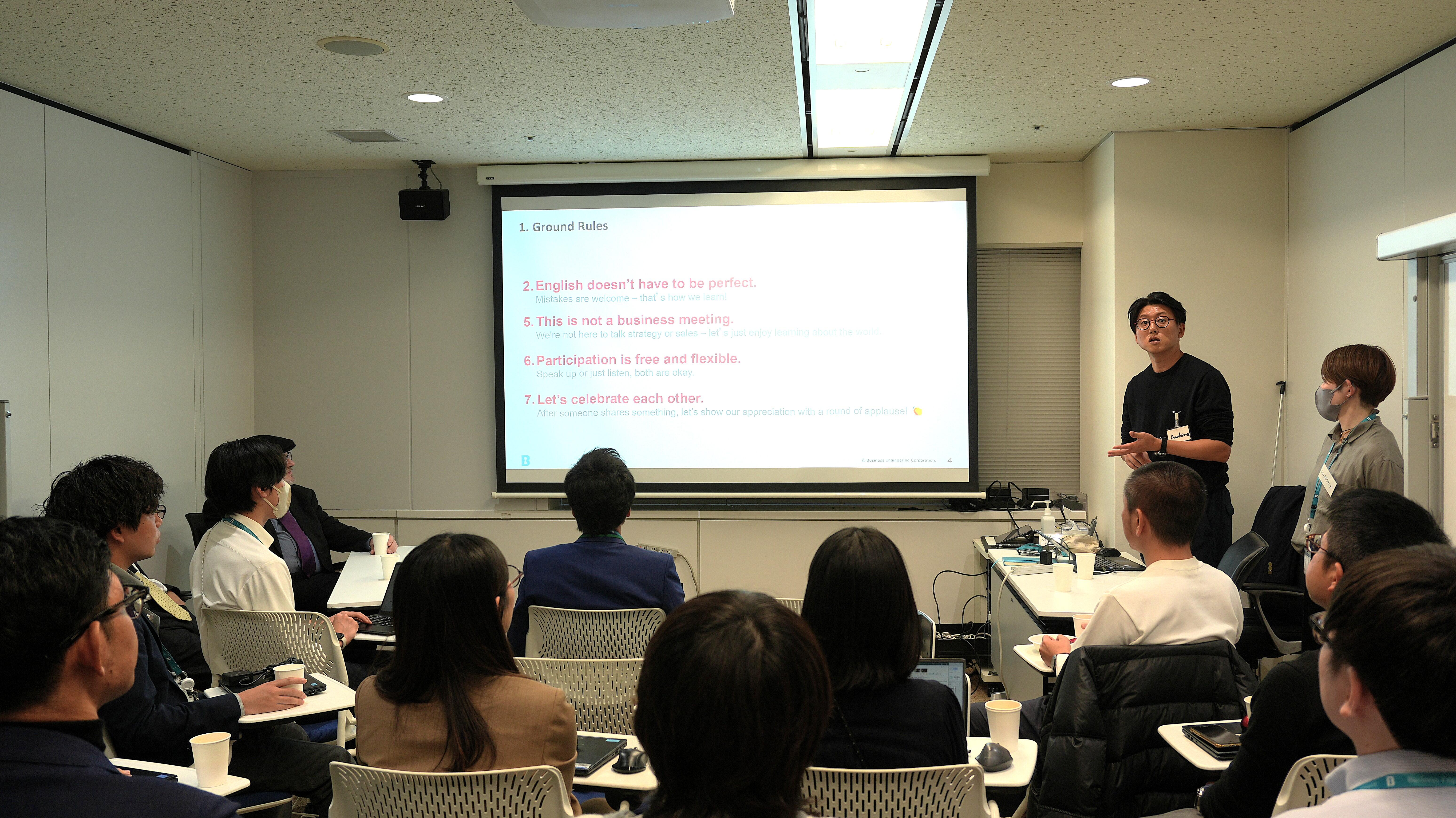話者:ビジネスエンジニアリング株式会社
ソリューション事業本部
デジタルエンタプライズ本部 エンタプライズソリューション2部
コンサルタント
堀 彰宏(ほり あきひろ)

プログラミングに対する情熱を持ち、SAPのABAP言語を用いたERPシステム開発者としてキャリアをスタートした堀 彰宏は、B-EN-Gへの転職を機にSCMコンサルタントとしての道を歩み始めた。そして現在、ある製造メーカーにおけるSAP S/4HANA刷新プロジェクトでリーダーを務め、繰り返し生産や個別受注など多様な生産方式に対応可能な汎用的システム構築を主導している。特にモノづくりの根幹であるBOMを起点としたモデル定義による課題解決などで卓越した手腕を発揮しており、その取り組みは原価管理の精緻化などの成果としても表れはじめている。
ERPシステム開発者からSCMコンサルタントへの転身
大学では経済学を学んだ堀彰宏だが、SAPのABAP(Advanced Business Application Programming)言語を用いたERPシステム開発者としてキャリアをスタートした。2013年に新卒入社した企業では、障害解析などを中心に基本設計から保守まで下流工程を主に経験してきたという。
そんな堀が大きな転機を迎えたのが、社会人4年目となった2017年のこと。B-EN-Gに転職し、SCMコンサルタントとして新たな道を歩み始めた。
「SAPのERPモジュールは大きく会計系と生産管理系に分けられますが、その中で私に合っていると感じたのが生産管理系でした。特にMRP(資材所要量計画)のロジックなどは非常に興味深く、SCM(サプライチェーン管理)の世界をとことん追求したいと考え、B-EN-Gに飛び込みました」(堀)

転職以降は、機械メーカーでのSAPのMM(在庫購買管理)/SD(販売管理)/FI(財務会計)各モジュールのアドオン開発・移行・保守や、化粧品メーカーでのS/4 HANA刷新、薬品メーカーでのSAP S/4HANA導入などを経験。そして現在、主に携わっているのが、鉄鋼業、機械工業など複数事業を持つ大手メーカーにおけるSAP S/4HANA刷新プロジェクトだ。PP(生産管理)/MM/CO(原価管理)/PS(プロジェクト管理)の各モジュールを対象とした標準生産管理システム構築のリーダーを務め、5年目を迎えた。
BOMを起点としたモデル定義による課題解決
現在携わっているプロジェクトは、量産品から個別受注生産まで手掛ける製造メーカーのSAP S/4HANA刷新である。その中で堀が重要な役割を担っているのが、業務要件と技術仕様の橋渡しだ。
複数の事業所をまたいだERPシステムのバージョンアップをリードし、繰り返し生産や個別受注など、多様な生産方式に対応可能な汎用的なシステムを構築することが当該プロジェクトの目標である。SAPの標準機能を活用しつつ、周辺システムとのインターフェースを整備して事業所ごと固有の業務要件に対応していく、というのが基本的なアプローチだ。
「最も重要なことは、システム導入のリードタイム短縮であり、加えて長期間にわたる安定稼働を支える運用の柔軟性と保守性を確保しなければなりません。全社展開可能なテンプレートを作成することで、これを実現します」(堀)
ただし、言うまでもなくこれは簡単なことではない。
「生産管理のモデルを検討する際に、まず考慮しなければならないのが生産形態です。しかし、お客様のご要望に基づいて生産形態をモデル化しようとしたところ、その定義の多様さから認識の相違が生じ、合意形成が一筋縄ではいきませんでした。また、生産形態に個別最適化すると、在庫ポイントまで固定化され、これをモデルの中心に据えるとシステムの柔軟性が失われてしまいます。これらがテンプレート化を阻む最初の壁となりました」(堀)
そこで、この課題解決のために堀が選択したのが、モノづくりの根幹であるBOM(部品構成表)を起点としたモデル定義である。

「これにより、製品コンセプトを実現する生産者の視点から、最適なエンジニアリング手法を選択することが可能になります。なぜなら、生産管理手法やサプライチェーンを通じた価値提供の方法そのものが、BOMの管理要領に大きく依存するためです」(堀)
BOMを軸にPLM、ERP、MESを効果的に結合
堀が強くこだわり選択した「BOMを起点としたモデル定義」について、その中身をさらに詳しく見てみよう。最大の狙いは、受注形態に応じてどの程度の個別設計が発生するのかを整理して把握する点にあるという。
「製品設計においては、顧客の要求仕様に対して個別設計で対応する『可変部分』と、変更されない『固定部分』が存在します。このうちの『固定部分』をいかに見出し、その部分を繰り返し生産の領域として定め、生産性を追求する仕組みをそこに構築できるかが、モノづくりにおいて重要な鍵を握ります。一方の『可変部分』についても、顧客からの要求リードタイムを満たせるよう、設計内容を柔軟に生産実行へつなげる仕組みを構築する必要があります」(堀)
堀を中心とするコンサルタントチームは具体的なソリューションとして、事前にBOMのモデル別の特徴を考慮したひな型となるプロセスフローを提供。さらに、このプロセスフローを実際に各事業所に実装する上でのフィット&ギャップのポイントを明確にしたチェック表を整備し、To-Beプロセスを導き出すための円滑な議論を主導した。
「各事業所の共通テーマとして何を議論のポイントとすべきかを押さえ、対応するコンサルタントのスキルや経験則のばらつきによる影響を低減することで、同等水準でのリードタイム短縮を目指しています」(堀)
また、デジタルスレッドの観点からも、BOMをテンプレートのキーファクターとすることは合理的だ。PLM(製品ライフサイクル管理)、ERP(統合基幹業務システム)、MES(製造実行システム)を効果的に結合する仕組みの中心には、必ずBOMが存在するからだ。各システムを統合したデータ分析から得たインサイトをもとに、運用改善につなげていくためにも、デジタルスレッドによる一貫したテーマが必要だ。

「例えば原価管理のデータ分析に際しても、いかに実際原価に基づいた情報を原価企画や原価改善へフィードバックしていくかが求められます。この仕組みもBOMの管理要領によって異なるため、一律のデータ分析の仕組みでは対応できず、デジタルスレッドによる個別対応が必要です」(堀)
原価管理の精緻化と今後の展望
上記のような多くの困難を乗り越える中で、具体的にどのような成果が見込まれているのだろうか。例えば、これまで「どんぶり勘定」に近い形で行われてきた原価管理の精緻化もその一つである。
「個別受注生産における標準原価分析を導入し、指図単位の原価の見える化に取り組んでいます。他の事業所にも展開することも視野に入れて標準化したソリューション開発を行い、SAP S/4HANA刷新による効果を創出していくのが目標です」(堀)
ただし、各事業所におけるデジタライゼーションに向けたテンプレート拡充はまだ十分とは言えず、B-EN-Gとしてもさらにサポート範囲を広げていく必要がある。
例えば個別受注生産の事業所の中でも、ある程度M-BOM(製造用部品構成表)管理が確立されている場合とそうでない場合では、アプローチが異なってくる。M-BOM管理ができていればSAPのPMMO(Project Manufacturing Management and Optimization)モジュールを活用してWBS要素をグループ化し、手配をまとめることで、コストの低減や実際原価の自動配分を推進可能だ。
一方、M-BOM管理が十分に浸透していない事業所に対しては、どのようにBOMを活用して改善するかを考える必要がある。例えば、MESによる製造管理ができているのであれば、SAPでは計画原価管理に適したダミーの工順を保持することでM-BOM作成の制約を外し、ERP連携による原価改善が可能になる。
「多様な設計方式や生産量、原価管理手法に応じたベストプラクティスを精査し、その知見を踏まえた最適なデータ分析手段を提供することが、今後の私たちコンサルタントチームの使命と考えています」(堀)
そうした中で堀は、技術的な厳しさと細部へのこだわりを持ちながら、後輩の指導・育成にも力を入れている。自身が深く理解した技術内容を咀嚼可能な粒度に分解し、チームメンバーに伝えることで、プロジェクト全体の理解度向上と品質確保を図っていく。
併せて注視しているのが、「SAP Business Suite」をはじめとする最新の市場トレンドだ。
「SAP Business Suiteのシステム構築には、アプリケーション、データ、AIの各要素が相互に補完し合い、利用価値を高める『フライホイール効果』が意図として組み込まれています。市場の変化に追従していくためにも、SAPのビジネス戦略をより深く理解することが重要です。特に現在もオンプレミス環境を利用しているお客様に対しては、プライベートクラウド、パブリッククラウドへの移行を段階的に推奨していく必要があります」(堀)
「変革を一歩ずつ確実に実現へ導いていくためには、私たちコンサルタント自身がマインドセットを転換しながら新たなテクノロジーをいち早く習得し、具体的な手段を講じてクラウドに対する懸念材料を解消していく必要があります」と堀は意を新たに示しつつ、多くの製造業のデジタル変革を先導していくSCMコンサルタントとしての高みを目指す構えだ。