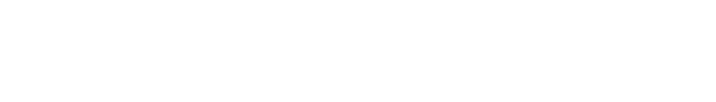プロジェクトの
流れ
B-EN-Gのシステム導入の流れと特徴がわかる、プロジェクトストーリー
PROLOGUE
東洋ギア工業は、創業80年を超える老舗自動車部品メーカーで、エンジンに用いられる特殊ギアの国内トップメーカーである。
同社の製品は市場でも高い評価を受けており、様々な完成車メーカーで採用されている。これまで、製造技術・設備・熟練工の3つの要素を活かして成長を続ける中で、電気自動車の普及・ガソリン車の減少といった市場変化にも対応し、モーターや制御装置の製造など新たな分野にも取り組んでいる。
そんな東洋ギア工業を支えるITシステムは、20年前に自社開発した独自システムを基盤としており、同社が成長を続ける裏側で多くの課題を抱えていた。
このプロジェクトストーリーはフィクションで、東洋ギア工業は架空の企業です。
はじまり
東洋ギア工業の、経営の意思決定に不可欠な製品販売状況・および製造状況のレポートは、各営業拠点・各工場から送られてくるデータを基に集計・作成しているが、多大な作業時間がかかっている。そのため、月半ばにようやく前月の情報が確認できる状況であり、実態が見えていない期間については、長年の実績や経験・作業者の勘に頼って適宜修正を行っている。しかし、これから市場競争に勝ち残っていくためには、ますます多様化・複雑化する市場のニーズを素早く正確にとらえていく必要があると考えている。
さらに、新たな製品の製造工程や得意先からの要望、法令改正への対応が発生する度にシステムの追加開発が必要となっており、レガシーな基幹システムでの事業運営自体が、業務改革を進めるボトルネックとなってしまっている。
今後さらなる飛躍を目指す同社は、創業100周年に現在の売上高を2倍にする目標を掲げている。その実現に向けて大きな鍵を握るこれらの課題をクリアする為、メーカーの心臓ともいえるERPシステムの刷新を決断した。そして、RFP*を実施の上、複数のSIerを比較検討することとなり、B-EN-GはこのRFPに参加をして提案を行うこととなった。
RFP:Request for Proposalの略。発注先を選定するために、必要な要件や実現したい業務を候補となるSIerに共有し、具体的な提案を依頼すること。

提案
RFPを受けて、B-EN-Gは25年超にわたり製造業・生産管理領域を中心とした国内トップクラスのシステム構築実績を持つSIerとして、また自社で生産管理領域に強いERPソフトウェア「mcframe」を保有しているベンダーとして、東洋ギア工業への提案業務に取り組んだ。提案フェーズは、B-EN-Gでは4名程度のメンバーで、1か月ほどの期間をかけて取り組むことが多い。
B-EN-Gは、東洋ギア工業が掲げるビジョンの実現と抱える課題の解決策として、自社ソフトウェアmcframeによるリアルタイムの営業情報・製造情報の可視化と、20年の間に複雑化した業務プロセスを見直して業務の標準化・全体最適化を目指す提案を行った。
実現を目指す具体的な内容は2つあった。1つは、販売管理・生産管理等のERPシステム領域をmcframeに置き換え、単なる受発注業務の管理だけではなく、市場のニーズを素早く正確にとらえる為の需給予測や、各工場・製造拠点の生産資源情報をリアルタイムに同期し、生産能力を踏まえた効率的な供給体制を実現する事である。
もう1つは、複雑な業務プロセスによって属人化が進んだ作業工程や、これに伴って肥大化したシステムを改善するため、mcframeが提供する標準機能に合わせて同社の業務プロセスを見つめ直すことで、業務の標準化・効率化・シンプル化・全体最適化とシステムのスリム化を実現する事である。
東洋ギア工業は複数社の提案の中でも、具体的で、且つ実現性・可用性を意識したB-EN-Gの提案内容を高く評価し、同社が描くビジョンの実現に最もマッチした導入パートナーとして、プロジェクトを共に進めていくことを決定した。

要件定義
プロジェクトを実現するために、システムに必要な機能などを定義するフェーズが、要件定義フェーズである。システム化する対象の業務を洗い出し、業務処理の手順やシステムの操作、入出力などの要件を整理し、要件定義書としてまとめていく。B-EN-Gでは7-8名程度のメンバーで、3か月程度の期間をかけて取り組むことが多い。
B-EN-Gは今回のプロジェクトにおいて、東洋ギア工業がこれまでに培ってきた、いわば競争力の源泉ともいえる製造技術・工程における強みやこだわりをより強固に実現するべく、追加開発での作りこみを行うことを提案した。一方で、スリム化を進めるべき業務については、Fit to Standard(追加開発を行わずに、業務内容をソフトウェアの標準機能に合わせていく手法)を徹底することを提案した。
東洋ギア工業は国内に工場が複数あるが、それぞれの工場で製造する品目が異なるため、その製造現場はまったく異なっている。B-EN-Gのプロジェクトマネージャー、ITコンサルタントは各工場に赴いて、製造担当者から作業工程のヒアリングを行い、追加開発をしてシステムを作りこむ部分と、mcframeの機能を活かして標準化すべき部分との取捨選択を行っていく。
それぞれの作業工程・プロセスの洗い出しにおいては、B-EN-Gが過去に手掛けた多数のプロジェクト実績の中から、特に業種、規模、業態等が近い分野のプロジェクトを参考にしつつ、最適な組み合わせを考えていく。
そして出来上がった案を東洋ギア工業に提案し、そこで受けたフィードバックや再度のヒアリングを基に改めて仕様の検討を行う、というプロセスを繰り返し、あるべき姿を共に描きながらどのような機能を実装していくかを定義していく。

設計
要件定義書を基に、システム開発の具体的な設計を行うフェーズが設計フェーズである。実際にユーザーが利用する画面の設計から、内部のプログラムの設計、データベースの設計など、さまざまな設計作業を行う。設計フェーズでは、整理した内容を設計書としてまとめていく。
B-EN-Gでは10名弱のメンバーで、3か月程度の期間をかけて取り組むことが多い。
まず、要件定義の内容を基にどのようなシステム構成としていくか等を決める、基本設計を行う。要件定義フェーズでは、システム管理者や製造管理者といった、主にユーザーを統括する立場のメンバーが中心となって進めることが多いが、設計フェーズでは、実際にシステムを多く利用する一般ユーザーの視点も踏まえつつ、利用場面を意識したシステム設計を行っていく必要がある。
東洋ギア工業のプロジェクトでは、同社の強みとする製造工程を管理する画面と実現したいシステム処理について、特に時間を掛けてしっかりとすり合わせを行っていく。
設計フェーズにおいても要件定義フェーズと同じように、固まった案を東洋ギア工業に提案し、それに対するフィードバックを基に再度設計の仕様を検討する、というプロセスを繰り返していく。
続く詳細設計では、基本設計を基にシステム内部の構造やデータの流れなど、ユーザーからは見えない細部の設計を行う。開発者の視点で、基本設計の内容をプログラミングできるレベルまで落とし込んでいくフェーズである。
設計書は、システムの構築段階だけでなく、システム稼働後の運用場面でも永続的に利用される重要な資料でもある。その為、なぜこのような設計となっているのか等、将来も含めたすべての関係者が同じように理解できる内容で構成する必要がある。

開発・テスト
開発フェーズでは、設計工程で作成した設計書をもとにプログラミングを行っていく。このフェーズはプロジェクトの中で最も規模が大きく、B-EN-Gでは協力会社を加えて30-40名程度のメンバーで、3か月程度の期間をかけて取り組むことが多い。
今回のプロジェクトでは、東洋ギア工業の強さの源泉である製造工程は、他社との差別化を図るために追加開発によってシステムを作りこんでいく。画面の動作から裏側の処理ロジックまで、設計書を基に丹念に開発を行っていく。新規開発部分は規模も大きくなる為、B-EN-Gメンバーは実装を担うプログラマーのタスク・進捗管理・品質管理を日々行い、懸念点は早めに対処をして進めていく。また、B-EN-Gの若手メンバーも開発スキルを得るために、実装業務に加わり、開発フェーズの経験を積む事も多い。
作りこみを行わない標準機能の領域においても、東洋ギア工業の製造業務がしっかりとmcframe上で実現できるよう、マスタ設定や項目設定を行う。また、実際の業務を想定したテストシナリオを用意し、データがきちんと流れて問題なく処理が進むかについて、B-EN-G側で入念に確認していく。
続いて東洋ギア工業側でも、B-EN-Gが構築したシステムを用いて、実際の業務を念頭に置いた受入テストを実施してもらう。この受入テストがうまく進められるように、B-EN-G側は綿密にフォローを行う。受入テストフェーズにおいても、B-EN-Gのメンバーは国内にある複数の工場に直接赴き、ユーザーサポートを行う事も多い。
操作に不慣れな工場ユーザーも多いため、従前のシステムからの変更点や、オペレーションにおいて注意が必要な点や、間違いが起きやすいと思われるポイント等を中心に、丁寧にサポートを行っていく。

移行・運用保守
完成したシステムの移行は、工場やシステム稼働が停止しているタイミングで行われるプロジェクトが多い。年末年始やGW、お盆休みといった長期休暇の期間を利用することが多く、B-EN-Gでは通常7-8名程度のメンバーで取り組んでいる。
B-EN-Gは移行後の安定したシステム運用を実現するために、運用保守を専門とするグループ会社(ビジネスシステムサービス株式会社)を設立して運用体制を整えている。システムのリリース後にスムーズな引継ぎを実現するため、導入フェーズのタイミング等で運用保守メンバーにもプロジェクトに加わってもらい、一緒にシステム導入や運用保守業務を進めていく。
運用保守フェーズでは、システムを切り替えた後も業務が問題なく進められているかの監視やサポートを行う。万が一システムにトラブルが発生した場合は即座に対応する必要があるため、システムの稼働後1か月ほどの期間は、B-EN-Gのメンバーが工場に赴きユーザーオペレーションのサポートやフォローを実施する。
そして安定稼働を見届けた後、プロジェクトメンバーは順次プロジェクトからリリースされ、休暇を挟んで新たなプロジェクトにアサインをされる。
これらがシステム導入プロジェクトの全体の流れであり、B-EN-Gでは1年から1年半をかけて取り組む事が多い。
基幹システムは一度導入して終わりではなく、企業活動を安定的に支えるために、また企業の成長を実現していくために、拡張・改修をしていくことが必要である。導入後にシステムの運用保守を行う中で、顧客から新たなプロジェクトのご依頼をいただくことも数多い。B-EN-Gの顧客には、10年・20年を超えて取引を続けている企業も多く、これはひとえに、共にものづくりを変えていくパートナーとして信頼を寄せていただいている証でもある。